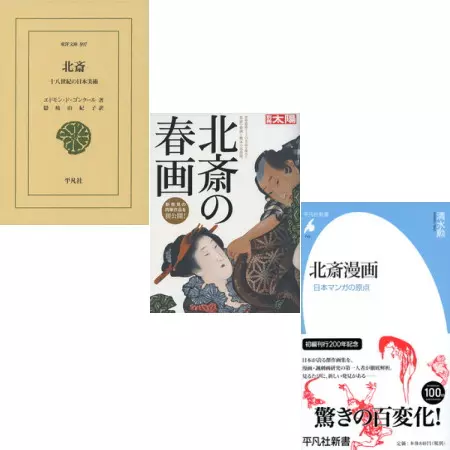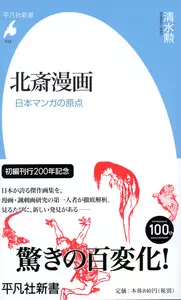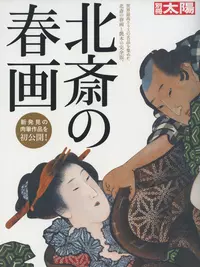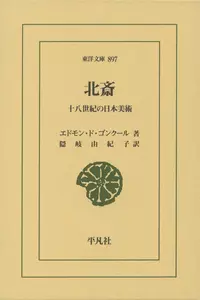北斎漫画はこれまで絵手本と考えられてきたが、じつは戯画・諷刺画の要素を多分に含み持ち、日本マンガの原点に位置づけられる。
本書では、漫画史研究の第一人者がコマ表現や吹き出し、キャラクター設定など、北斎の先駆的な技法に着目しながらその豊饒なる世界を徹底解説。一方、北斎漫画は当時の江戸の風俗を写しだしたビジュアル百科のようでもある。
1点1点絵を文化史の視点から見直すことで、江戸の人びとの知られざる豊かな暮らしも浮かび上がる。
200年の時を経てもなお読み継がれる江戸のベストセラー本の魅力がいま、明らかに。図版150点掲載。
北斎漫画 日本マンガの原点 目次
▶はしがき第Ⅰ部 全体像
第1章 『北斎漫画』の成り立ち
日本漫画三〇〇年史/『北斎漫画』のはじまり/全一五編としての『北斎漫画』
第2章 絵手本か戯画本か
外国人の見方/各編の特徴/スケッチとドラマ
第3章 『北斎漫画』の「漫画」とは
漫画語/ポンチと漫画/現代的意味の「漫画」誕生
第4章 北斎が見てきた戯画本
戯画の商品化/『狂画苑』に注目した北斎
第Ⅱ部 戯画・諷刺画 各論
第5章 ナンセンスな面白さ
ナンセンス漫画/何となくおかしい/大いに笑わせる/刺激的で怖い
第6章 コマ表現の独創性
コマ枠表現/四コマ漫画の源流/ストーリー漫画の試み
第7章 権威・権力に放たれた諷刺の矢
諷刺画の生まれる背景/寛政の改革/天保の改革/『北斎漫画』一二編の諷刺画/歌川広景への影響
第8章 キャラクター・ドラマ作りの名手
戯画キャラクター/弁慶と牛若丸/浦島太郎と桃太郎/個性豊かな女性たち/江戸の動物戯画/虎と象/獅子 二題/風神・雷神/動物キャラクター/誇張と擬人化
第9章 江戸時代ビジュアル百科
日常の寸景/妖怪変化/福神/知的好奇心/著名人
第10章 永遠なる『北斎漫画』
現代的表現/吹き出し/動的表現/絵を動かす/逆転の発想/漫画大国の基盤/永遠の『北斎漫画』
▶あとがき
『北斎漫画』略史/参考文献
19世紀フランスの文豪エドモン・ド・ゴンクールが、江戸を代表する天才絵師の全容を物語る。
今では世界的に著名な北斎を、1世紀以上前に評価し愛して書かれた名著。
葛飾北斎
宝暦10年9月23日〈1760年10月31日〉? - 嘉永2年4月18日〈1849年5月10日〉は、江戸時代後期の浮世絵師。化政文化を代表する一人。
代表作に『富嶽三十六景』や『北斎漫画』があり、世界的にも著名な画家である。
森羅万象を描き、生涯に3万点を超える作品を発表した。若い時から意欲的であり、版画のほか、肉筆浮世絵にも傑出していた。
しかし、北斎の絵師としての地位は「富嶽三十六景」の発表により、不動のものとなっただけでなく、風景画にも新生面を開いた。
北斎は、浮世絵で高い芸術性を表したが、大衆的な『北斎漫画』の中にも彼の卓越した描写力を見ることができる。さらに、読本(よみほん)・挿絵芸術に新機軸を見出したことや、『北斎漫画』を始めとする絵本を多数発表したこと、毛筆による形態描出に敏腕を奮ったことなどは、絵画技術の普及や庶民教育にも益するところ大であった。
葛飾派の祖となり、後には、フィンセント・ファン・ゴッホなどの印象派画壇の芸術家を始め、工芸家や音楽家にも影響を与えている。シーボルト事件では摘発されそうになったが、川原慶賀が身代わりとなり、難を逃れている。
ありとあらゆるものを描き尽くそうとした北斎は、晩年、銅版画やガラス絵も研究、試みたようである。また、油絵に対しても関心が強かったが、長いその生涯においても、遂に果たせなかった。
1999年には、アメリカ合衆国の雑誌である『ライフ』の企画「この1000年で最も重要な功績を残した世界の人物100人」で、日本人として唯一86位にランクインした。門人の数は極めて多く、孫弟子も含めて200人に近いといわれる。
»通販サイトへ